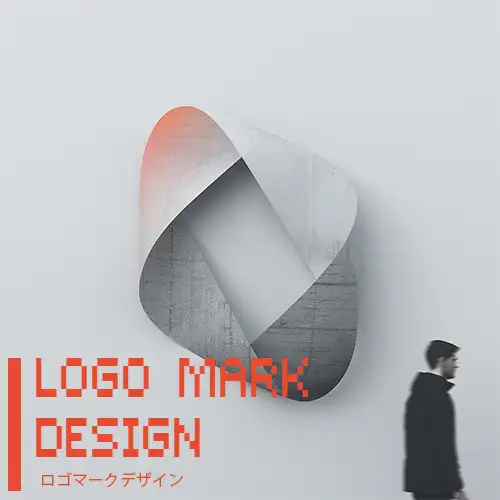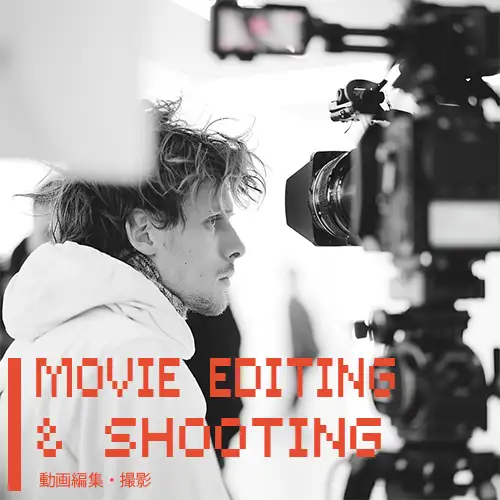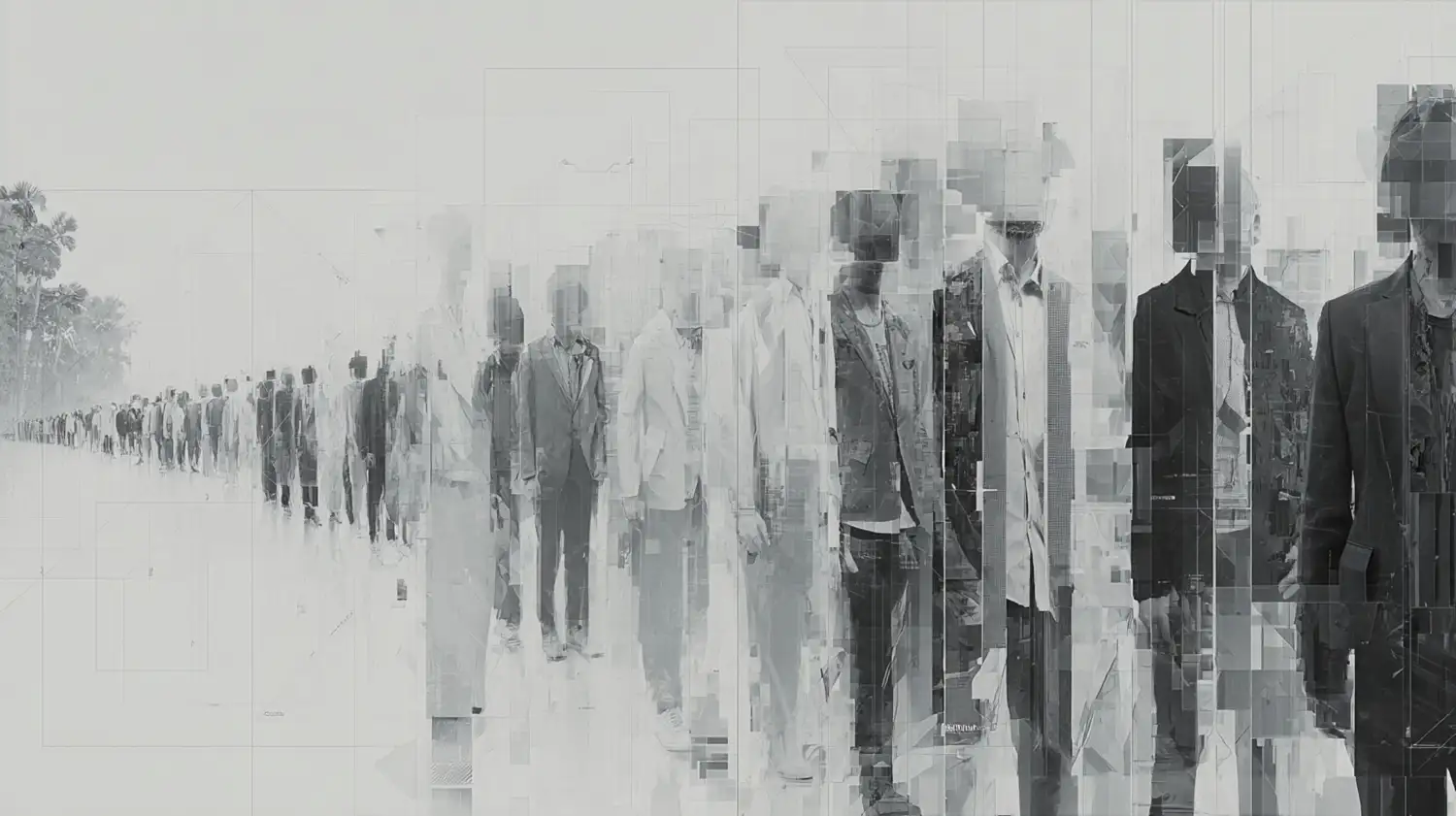51%が勝っても、残り49%はモヤモヤ……あなたも経験ありませんか?
多数決のお話です。
多数決の3つの限界
多数決には3つの限界があります。
① 51% 対 49% でも前者が“正解”とされ、49% の声がゼロ扱いになる
② 重要度の高い問題も、低い問題も重みが同じ
③ 一度多数決で結果が出ると、すぐに見直せない。
このような問題をテクノロジーで回避できるのではないか?という考えが
Plurality(プルラリティ)です。
プルラリティとは?
プルラリティの定義は
- 技術と民主主義を統合する包括的なパラダイム
- 多様性を力づけ、差異を架け橋する技術的アプローチ
- 協力的テクノロジーによる民主的統治の革新
- 社会的分裂を超えた集合知の実現
つまり、プルラリティは単なる意思決定手法ではなく、テクノロジーと民主主義の関係性を根本的に再構築する思想・実践体系なのです。
全体を話すと長くなりすぎるので、今回の動画では プルラリティの “意思決定プロセス” 部分を中心に取り上げます。
プルラリティは“重なり”と“熱量”を同時に測る新しい意思決定フレームワークになります。
まず AI が意見をまとめ、次に“投票クレジット”で投票、最後に結果を即公開。
調整コストが下がり、満足度も上がるメリットがあります。
近年耳にする「多様性」は、様々な異なる意見や背景が存在する“状態”を指します。一方、プルラリティが目指す「多元性」は、それらの多様な意見が対立・分断するのではなく、それぞれが尊重され、共存しながらより良い合意を形成していく“あり方”や“プロセス”を意味します。
例えば、
- 何を言っても誰かに怒られる“早押し批判ゲーム”になる「ポリコレ疲れ」
- 誰が一番“被害者”かでポイント争奪が始まる「アイデンティティ・オークション」
- 小さな合意に膨大な時間とストレスがかかる「協調コスト爆増」
このような多様性の暴走モードを経験された方も多いかと思います。
プルラリティは、この多様性の意思決定の際にも役立つ可能性が高いのです。
このプルラリティは、現在オープンソース書籍になっています。
中心になってまとめたのは、オードリー・タン氏とE. グレン・ワイル氏。
オードリー・タン氏は 台湾の初代デジタル大臣。「誰一人取り残さないテック公共インフラ」を推進し、世界的に高い評価を得ています。
E. グレン・ワイル氏は
Microsoft Research 首席研究員で、Quadratic Voting の提唱者です。
ブロックチェーン界や公共政策学者も続々賛同していているのが、このプルラリティです。
プルラリティの意思決定プロセスの3ステップ
1)AI 要約 (pol.is)
pol.is とは?
クラウドで動くオープンソース熟議プラットフォーム。参加者のコメントをリアルタイムでクラスタリングし、賛否・共感マップを自動生成します。
2)Quadratic Voting(2乗コスト投票)
各参加者に 10 枚=10 クレジット を配布します。
投じる“票”は自分で決定。ただしk票入れるには、k²枚のクレジットが必要です。
例:1 票→1 枚、2 票→4 枚、3 票→9 枚。
あなたが2票を一人で入れる影響=他の2人が1票ずつ入れる影響と同じ2票ですが、コストはあなたに集中します。
つまり“声の大きなクレーマー”が多数票を独占しようとすると、自分だけ大量クレジット消費が必要になり、簡単には支配できません。
3)Liquid Democracy(テーマ別委任)
環境政策はエコ団体に、税制は信頼する友人にと言った感じで、ワンタップで委任と直投票を切り替え可能。
この3ステップになります。
適応例
内部試算例として“市民公園リニューアル”ミニシミュレーションをした場合
従来の会議の場合は
期間:6 週間
会議回数:5 回
満足度: 60%
これに対して、プルラリティ方式の場合は
期間:2 週間
オンライン:1 回
満足度: 85%
調整コストが 3分の1、満足度は +25pt。見える化と熱量反映がキーとなります。
プルラリティは色々なスケールに落とし込むことが可能です。
企業経営の場合は、社内 OKR(目標管理指標)や福利厚生優先度を“投票クレジット”で決定。
NPO/自治体の場合は、限られた予算の配分を市民と共同設計。
オンラインコミュニティの場合は、イベント内容や新機能の優先度をリアルタイム反映。
このように、民主主義1番の多数決という暴君を、なめらかにすることを可能にします。
民主主義はいま“致し方ないベスト”と言われるレガシー状態。プルラリティも万能薬ではありませんが、現時点で最も有力なアップデート候補の一つです。
まずは 3 ステップで誰でも小さく試せます。
①無料 pol.is でアンケート
②2乗コスト投票を Google スプレッドで実験
③結果を Notion で公開
こんな形です。
今回の動画では プルラリティの “意思決定プロセス” 部分を中心に取り上げました。
全体像には デジタル ID・データ主権・公共インフラ など広範な要素が含まれるので、プルラリティを詳しく学びたい方は、原文は GitHub で PDF 無料ダウンロード出来ます。
日本語翻訳は紙書籍も発売中。全文が OSS ライセンスで公開されています。
Just be hopeful.