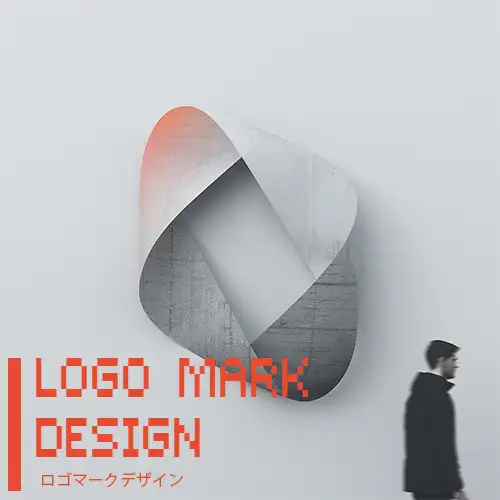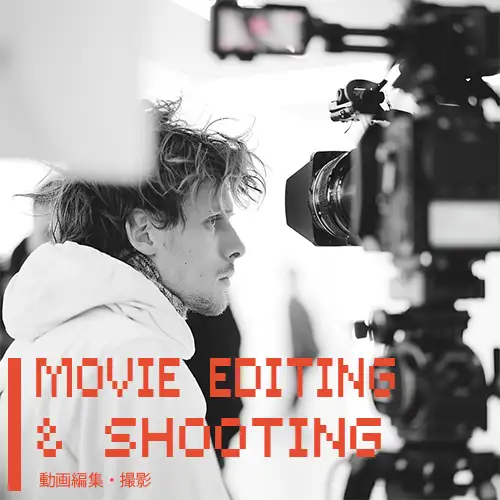まず最初に、この文章に最終的な答えはありません。
そもそも、物事に答えなどないと言うのが私の考えです。
しかし、物事を考えるのは好きです。
今、現時点で「自分」は何をどう感じ、何を考えているのかを整理するために
月に一度の執筆のようなものを10年以上続けています。
また、これが他の誰かの思考のきっかけになることがあれば幸いに思うことと
自分が亡き時代に、あの時、父親は何を考えていたのかを子供達が後からでも見直し
思考のリレーが出来たらいいなと2年前から、これも月に一度動画に残しております。
では、本題に入ります。
AI革命は、産業革命を超えるスピードで社会に影響を与えていることはよく言われ
多くの人も同じように感じていると思います。
しかし、これを数値などで知るにはまだ難しい。
1760年〜1860年の産業革命100年間では一人当たりのGDPが1.6〜1.7倍に引き上がった数字は出ていますが、ChatGPT 3.5がリリースされた2022年末から2025年までの一人当たりGDPの成長率は約1.1倍で、AIによる成長というより、世界的なインフレによる結果的成長の数値という見方が現段階では妥当と考えます。
AIの登場により、知識の民主化が始まり、これまで一部の専門家などの独占していた知識や技術が、多くの人が手にすることが出来るようになりました。
こうした変化は、結果的に「リベラル的価値観」を広げているとも感じます。
私と同じような疑問を持つ方もいるかと思いますが
この、リベラル優勢かと思われる土壌で、世界では保守派が急速に支持を伸ばしている現状。
これは偶然なのか?
それとも必然なのか?
今回は、この辺を考えていこうと思います。
第1章:AI革命が生む「変化疲れ」
AIは私たちに自由をもたらした一方で、大きな“不安”も同時に生み出しましたと思います。
・情報の爆発的拡大による、何が正しいかわからない社会
・職業や産業の再編による、「AI失業」の不安
社会の変化があまりに早すぎで、多くの人が“ついていけない”と感じ始めているのも事実です。
これだけ、コンピューターが一般化された社会でも実際には「ブラウザ」の意味が通じないことも多々あります。それがいけないとは何も思いませんが、その現実の中でAIは理解できませんし、使いこなすのはとても困難なことと思います。
このような心理的ストレス、つまり“変化疲れ”が、“安定”や“秩序”を求める保守的な価値観を後押ししている可能性もひとつ考えられます。
第2章:保守化が進むもう一つの理由
とはいえ、世界的な保守化は変化疲れによる“古い価値観への回帰”だけが理由とは思えません。
リベラルの理想の暴走も考えられます。
・ESG投資・脱炭素政策の急加速による、産業界への過大な負担
・ジェンダーや多様性を巡る急進的政策による、社会の準備が追いつかない状態
・IT富裕層中心のリベラル推進による、 格差の拡大放置
・グローバル化による、「自国の利益を奪われる」という不安増幅
理想が正しいか、誤りかの議論は置いておいて
現実が追いつかないまま価値観だけ先行すれば、反動が起きるのは必然かとも思います。
こうして、極端なリベラルの揺り戻しとして、保守派が支持を伸ばしているという面もあるかも知れません。
第3章:極端がもたらすリスク
危険なのは、当然ですが保守やリベラルということではなく
それが極端に振れた時ではないでしょうか?
米国で例えると、極左は数年前の状態で、どんな社会になったかは記憶に新しいと思います。
極右が現在の状態のイメージに近い気がします。
先日、米国大統領が国防総省を戦争省と呼称するという署名にサインしました。
今回のはまだ正式な名称変更ではなく、あくまで呼称です。
正式に名称変更する場合は、立法措置が必要で、大統領令は強力ではありますが、単独で法を変更するまでの力は持っていません。
元々、国防総省は1947年からの名称で、その前は陸軍と空軍を管轄する戦争省と
海軍を管轄する海軍省という名称でした。
以前使用していた名称とはいえ、現代を生きる私としては物騒な印象しかありません。
世界大戦の過ちを繰り返さないことを切に願います。
生きるために必要な水や塩であっても、極端に摂取すれば害があります。
何事も、ほどほどが良いのではと思うのが個人的な感想です。
第4章:右や左以外の道はないのか?
右に振れて失敗し、左に振れて失敗し、また右へ。
人類はこの揺り戻しを繰り返してきた印象です。
先日、米国で起きた痛ましい事件。
その影響で、分断を通り越して、プチ内戦に入ったのかと思わされる現象も起きています。
人が集まれば、そこに意見の違いがあるのは当然。
それを、分断とするのではなくバランスの取れた調和の方向に進む道はないのか?
以前動画で、Pluralityの紹介をさせていただきました。
試してみる価値は充分にあると思う一方、政策ごとの投票や委任には、個人の知識がキーになる為、先ほどの「ブラウザ」の話と似たような話にならないでもない気もしていますが、そろそろ何らかの変化が必要な時期だと感じています。
しかし、その変化の担い手は誰なのでしょうか?
AIでしょうか?
それとも、怒りをエネルギーに変えた、誰か強いリーダーでしょうか?
私は、そうではないと信じたい。
”悪い状況こそ、人間の真価が問われる”という言葉の通り
今こそ私たち一人ひとりの理性が試されているのではないでしょうか。
AIに「人間も捨てたもんじゃないな」と思わせるのか
「やっぱり人間はダメだ」と判断させるのか。
その分水嶺に、私たちは立っている気がします。
仲良くいこうよブラザーと、思う今日この頃です。
Just be hopeful.