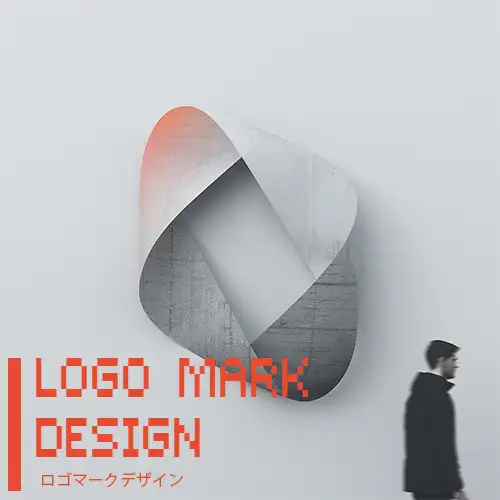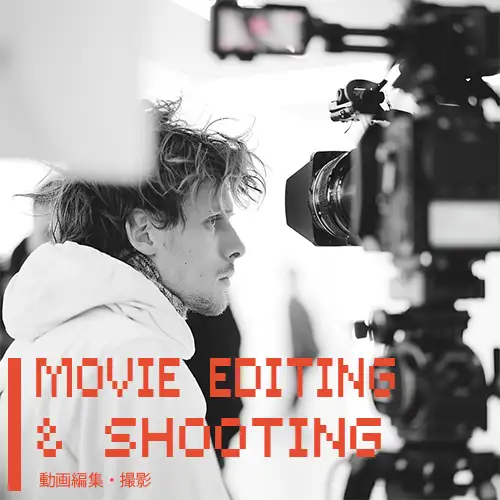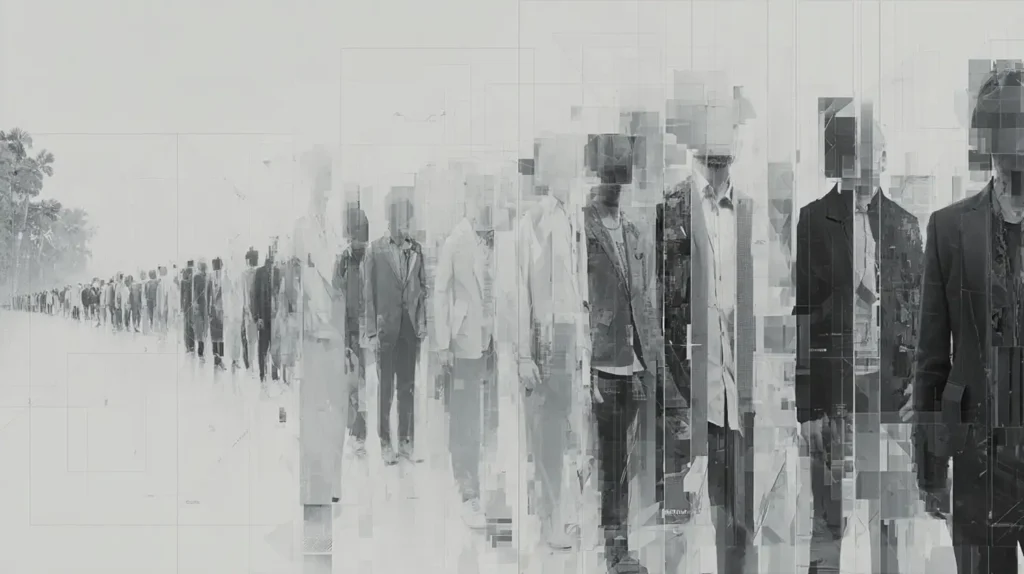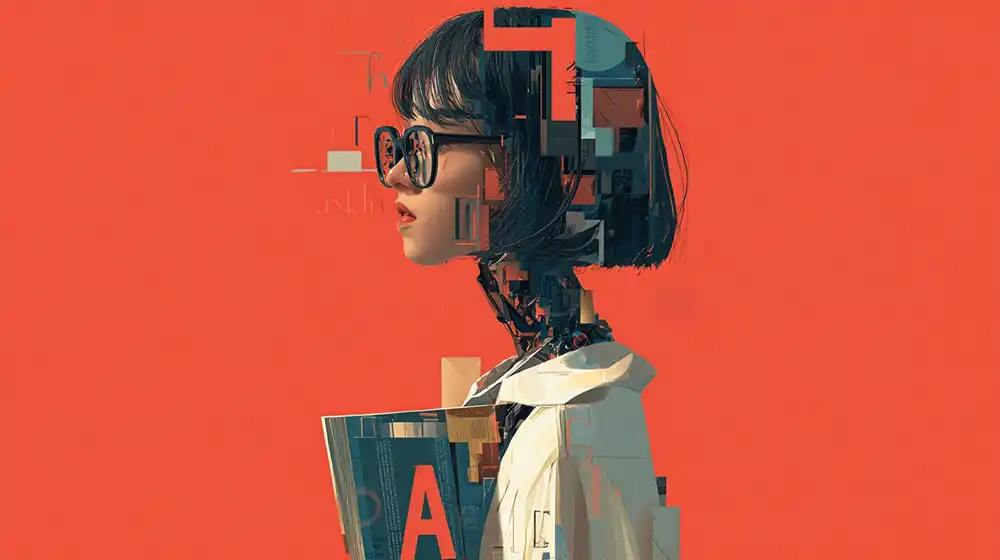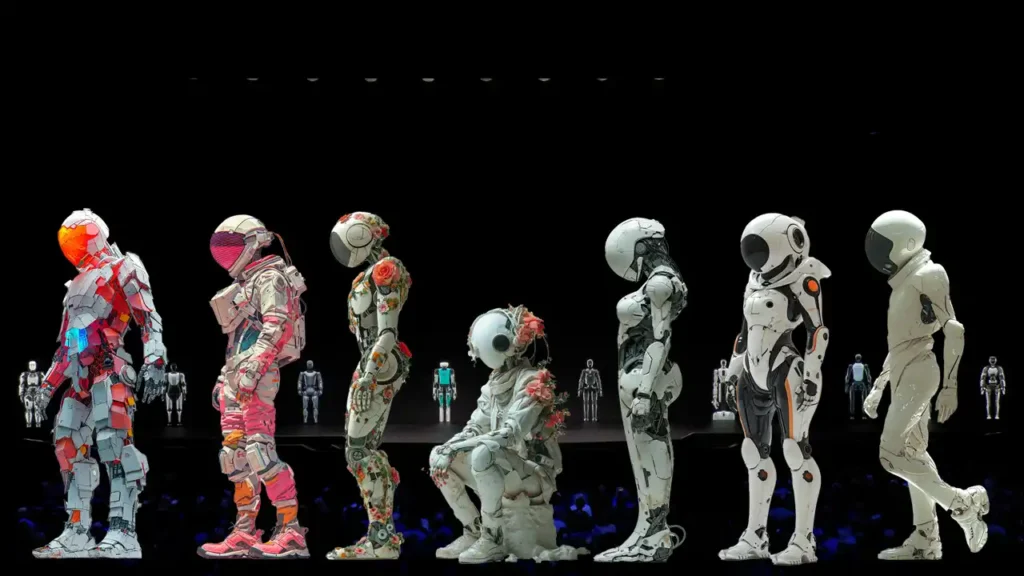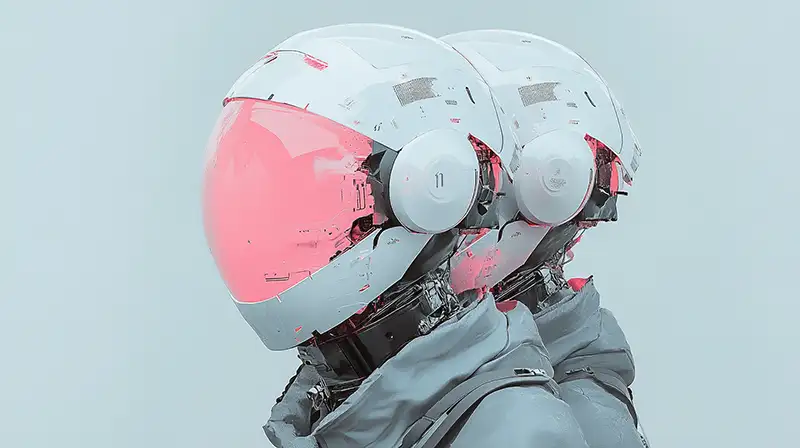最近、どこに行ってもよく聞く話は「人材・人手不足」についてです。
・人が集まらない問題
・人が辞めてしまう問題
だいたい、この2点のことが多いです。
今回は、この2点についての、わたしの持論・解決策をお話しさせていただきます。
1.人材が集まらない問題
「どこで聞いても人手不足、少子高齢化でどうしようもない。」
よく聞くお話しです。
まず、人材が集まらない時のポイントは3つ。
・少子高齢化は社会の問題であり、企業の問題ではない
・安く雇える都合の良い人材を求めすぎている
・そもそも人材不足ではなくIT化不足
ひとつづつ解説していきます。
①少子高齢化は社会の問題であり、企業の問題ではない
少子高齢化と人材不足を結びつけるのは
カッコつけて言うと「外的帰属」とか「自己奉仕バイアス」とかいいますが
要は、悪い結果を他人のせいにするということ。
ミクロの問題に対処できない時に、マクロの問題にする。
最近はこのようなマクロ依存が強くなっている傾向を感じます。
近年の政治への関心の高まりなんかも、ある意味そうだと思います。
仕事の問題、パートナーとの問題、子供の問題、体調の問題。
本来は「自分の足元で向き合うべきミクロの問題」から目を背けるために、
マクロな問題に声をあげる。そんな構図も見え隠れします。
「自己保護」が根源としてある人類にとって、当然の思考すり替えだと思いますが問題は解決しません。
”他人のせいにしてはいけない”
誰もが幼少時代に教えられたと思います。
親の問題でも、環境の問題でも、社会の問題でもありません。
「わたしの問題です。」
そもそも「問題」をマイナス視すること自体がもったいないと思います。
問題なんて、直したり解決すれば良いだけです。
ただの「醍醐味」です。
②安く雇える都合の良い人材を求めすぎている
会社側が都合の良い人材を求めるように、求職者は自分に都合の良い会社を求めています。
…そりゃ、マッチングしませんよね。
給与や待遇が悪くて、優秀な人材。
宝くじより当たらんと思います。
大谷選手が結婚した時に、ガチで落胆した女性がたくさんいたらしいですが
いや、ワンチャンないでしょと、これ以上ない軽蔑の眼差しで見ていた男性。
同じことやってますねん。
③そもそも人材不足ではなくIT化不足
これが結構根本的な問題の場合が多い気がしてます。
「なんでそんな作業してるんですか?」ってことが、かなり多いのが現実です。
タブレットを使って紙を減らせば DX だと思っている企業が多い中で、
本当の意味での IT 化や AI 化が現実問題かなり難しいのは、よくわかっています。
しかし、人材不足を本当に解消できる唯一の手段は、ここにしかないとも思います。
タブレットもスマホもそうですが、所詮ユーザーにしかなれないです。
プレイヤーになるにはPC一択です。
これと同様に、AIの無料ユーザーは、所詮ユーザーにしかなれないです。
プレイヤーになるには課金一択です。
わたしは、ユーザーが悪いとは1ミリも思っていません。
プレイヤーになりたがっているのに、行動がずっと「ユーザー」のままの人を見ていると
「なんなん?」とは思います。
2.人が辞めてしまう問題
まずポイント3つ
・人は辞めるということ
・やる気搾取は御法度
・せっかく育てたのに辞めちゃう
①人は辞めるということ
人は固定的なものではなく、流動的なものです。
人が辞めてショックなのは、わかります。
しかし、辞める前提で考える必要もあります。
中小企業の離職率で見ると、ざっくりこんな感じです。
企業規模(従業員数) 離職率
300~999人 16.1%
100~299人 19.0%
30~99人 16.0%
5~29人 15.6%
※出典:厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況
これはあくまで平均で、もちろん業種によって大きく異なります。
離職率が高い業種
・宿泊業、飲食サービス業:26.6%
・生活関連サービス業、娯楽業:28.1%
離職率が低い業種
・製造業:9.7%
・金融業、保険業:10.5%
けっこう簡単に調べられるので、御社の業種で一度見てみてください。
平均の離職率と同等または低ければ、そこまで気にすることじゃないと思います。
一方で、平均より高い場合は、給与や待遇、人間関係などの問題がある可能性は高いです。
もちろん離職率は年齢によっても変わります。
年齢階級 離職率
19歳以下 43.1%
20~24歳 29.2%
25~29歳 21.8%
30~34歳 16.9%
35~39歳 14.8%
40~44歳 13.0%
45~49歳 12.0%
50~54歳 11.2%
55~59歳 10.3%
60~64歳 17.5%
65歳以上 14.1%
(参考) 全体平均15.0%
年齢が上がるにつれて、離職率が低下する傾向は、はっきりと出ています。
なので、離職率を下げたい!だけが目的であれば、高齢者の雇用でバッチリ解決できます(笑)
次に、中小企業の平均勤続年数は以下の通りです。
男性:10~13年
女性: 7~10年
※厚生労働省の調査による
ここで、注意する点は、離職率、平均勤続年は似て非なるものということ。
離職率は「人の流れ(フロー)」を見ているのに対して
平均年数は「今いる人(ストック)」を見ています。
この二つが混在すると肌感覚とのズレが起きます。
特に平均は、上下をカットしたトリム平均ではないので、平均値のマジックがあります。
「平均勤続年数」は、それ単体で見ると肌感覚とズレますが、「離職率」とセットで見ることで初めて意味を持つ(例:「平均は長いのに離職率が高い」=ベテランはいるが若手が辞めている会社)と理解するのがよいかと思います。
数値を見るだけで、数値が読めない人は、数値は追いかけない方が良いです。
結論で言うと、数値を読んで平均以下なら気になしない。
数値を読めない人は、そもそも気にしない。
これが一番です。
②やる気搾取は御法度
やる気搾取は大きく分けて2パターンあると思ってます。
・肩書を簡単にあげるパターン
・あげる肩書がない、給与があげられない、だから教育パターン
1)肩書を簡単にあげるパターン
⚪︎⚪︎リーダーとか、よく見かけますね。
責任だけあって、給与と権限が比例してない一番悪質なやる気搾取パターンです。
責任と給与と権限は比例して初めて成り立ちます。
このての企業はすぐに人が辞める傾向を強く感じます。
2)あげる肩書がない、給与があげられない、だから教育パターン
1)よりは良い気もしますが、あげれる肩書きがない、給与もあげられない、だから社員のモチベが上がらない
では教育して、モチベを上げよう。
んー幼稚園の頑張ったらシール貰えるみたいな感じは、大人には通用しないと思います。
先も述べましたが、モチベを上げるには
責任と給与と権限は比例して初めて成り立ちます。
やる気搾取は、見ていて一番美しくないとわたしは思います。
③せっかく育てたのに辞めちゃう
これもよく聞きますね。
ガッカリする気持ちはよくわかります。
わたしごとですが、ベンチャー企業時代に社長とぶつかった経験があります。
当時は「肩書は渡す・給与は渡す・しかし教育は徹底しない」という方針の企業でした。
幹部として、もっと社員教育を強めたかったわたしに社長が言いました。
「教育して成長すると、人は辞めるんだよ。人を集めるのにどれだけお金がかかると思ってる。」
はぁああああぁぁ?
と、当時は思いましたね。
器の小さい社長だなと。
「辞めたっていいじゃないですか、いつか今の自分があるのは
あの会社で厳しくしてもらえたからと思ってもらえれば」と、言いましたが
わかってねぇなぁいう顔をされ、価値観の違いでそこから独立に向かいました。
でもね、20年以上経ってみて、あの時の社長の発言は「企業」としては間違ってなかったと思うんですよ。
現に今や5000人規模の企業になっていますからね。
企業とは「利益を上げるもの」と定義したとき、あの発言と決断は、正しいとも言えるわけです。
高いポジション、高い給与。 人は責任とお金と安心を抱え込んだまま、自分で動けなくなっていく。
そうやって“辞められない人”を増やすのが、経営としては一番ラクなんだろうな、とも思います。
でも、やらんけど。
わたしは、「いつ辞めてもいいし、辞めてもこの経験は血肉になる」 そんな時間を一緒に過ごせる会社の方が、少しだけ人間らしくて好きです。
人は辞めます。ITも進化します。 少子高齢化も、すぐには止まりません。
それでも、自分の会社の“人手不足”くらいは、 「時代のせい」じゃなく、自分たちの手でなんとかしていきたい。
Just be hopeful.